トピックス

12月8日 成道会
12月8日(月曜日)午後1時より本堂にて成道会を厳修いたしました。 成道会は、お釈迦さまがお悟りを開かれたことを祝う法要です。 本年は臨済宗の僧侶によりお勤めいたしました。 法要後は小豆粥をお接待致しました。 ご参列、あ…

11月24日 浄土宗念仏会
11月24日(月)10時より副本堂にて「浄土宗念仏会」を営みました。 浄土宗4僧が出仕し、ご参列の皆さまとお経本をお称えしました。 ご参列いただいた皆様におこわをお接待致しました。 ご参列有り難うございました。合掌

11月18日 浄土真宗報恩講
11月18日(火曜日)午前11時00分より浄土真宗報恩講を厳修致しました。 浄土真宗の宗祖(開祖)親鸞聖人は 西暦1262年陰暦11月28日に往生の素懐を遂げられました。 阿弥陀さまの教えをお伝え下さった親鸞聖人のご命日…

【12月のお話し】
立山連峰をご神体と仰ぐ神仏習合の霊場として開かれた立山修験は、聖者を導いた熊を阿弥陀如来の化身と仰ぎ、極楽と地獄を併わせた修験道の信仰を今に伝えます。 戦国時代から加賀藩支配となったことにより前田家の祈祷寺としての性格が…
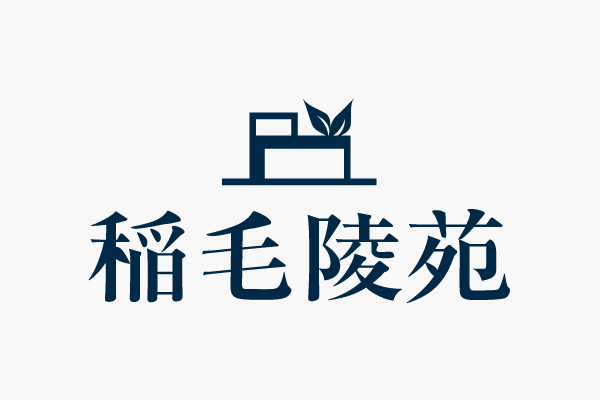
修正会のお知らせ
古来正月初めの法要では、旧年の悪を正し、新年の息災を祈る風習が伝えられております。 当山では来たる新年がご多幸でありますよう下記のとおり修正会(しゅしょうえ)を営みます。 当日は仏教各宗旨の僧侶が出仕し、ご参列者お一人お…
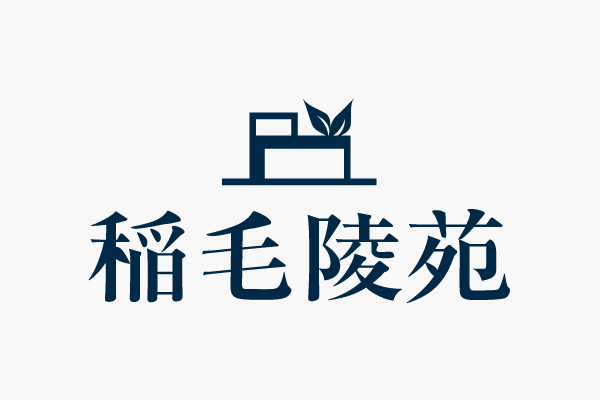
成道会の御案内
時下愈々ご健勝の御事とお慶び申し上げます。 お釈迦さまは12月8日に悟りを開かれ仏陀となられました。 これを仏教では成道と申します。 当山ではお釈迦さまの成道を祝い、下記のとおり成道会を営みます。 なお、当日は成道の故事…

【11月のお話し】
高市首相が総裁選中の発言で話題となった奈良公園の「鹿」は、藤原摂関家のトーテム(特定の集団や人物、部族や血縁と宗教的に結び付けられた動物や植物などの象徴のこと)で、奈良時代に鹿島神が常陸の国から白鹿に乗り奈良の都へ来て春…

「気持ちを伝える手紙」のご供養
三階に設置しております「気持ちを伝える手紙箱」には日々多くのお手紙が投函され、僧侶によって仏さまにお届けしております。 この度は日蓮宗の僧侶による心からのご供養の後、お預かりしたお手紙をお焚き上げしました。 合掌





